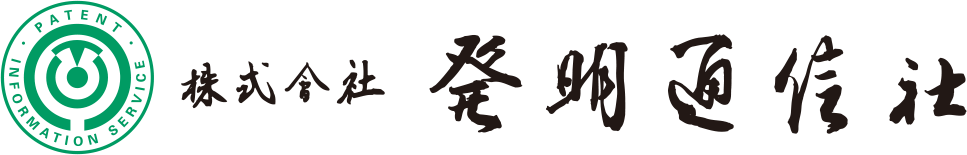産学連携で北里研究所に250億円を導入した大村智博士 ―(上)
産学連携の言葉もなかった時代から始める
大学・研究機関の研究室で生まれた学術的な研究成果を、社会で役立てるため産業現場に成果を移転して実用化に貢献する。これが産学連携であ る。1990年代から本格的に始まったIT(情報科学)産業革命は、従来の基礎研究の成果が実用化されるまでのタイムラグ(時間差)がきわめて短縮されてきた。
大学で基礎研究の成果として出たものがすぐに実用化されるような時代になってきた。一見、大学の研究室は企業の下請けのように見えることもある。しかしそれは外見的にそう見えるだけで、学問の創造と学問の自由は失われていない。
近年のノーベル賞受賞業績は、実用化になってから1兆円市場を作るような基礎研究の成果を出さないと受賞できないとも言われるようになっている。つまりノーベル賞でも実用化での成果が重視されているということだ。
北里研究所名誉理事長の大村智博士は今年76歳になり、現役の研究者から司令塔へと役割を移動しているが、その発想と後継者育成への情熱はますます 熱くなっている。大村博士が産学連携で250億円以上もの特許ロイヤリティ収益を北里研究所に還流させた実績はあまり日本では語られていない。ここで3回 にわたって、大村博士の発明研究と産学連携の話をしてみたい。
大村博士の研究は、土壌中に生息する微生物がつくる化学物質の中から、役に立つものを探し出す研究だ。これまで国内各地の土壌から9属、31種の新しい微生物を発見し、微生物が作り出す化学物質を450種も見つけた。世界でも断トツの実績である。
微生物の作った化学物質を役立てることを歴史的に最初にやった人は、イギリスのアレクサンダー・フレミングであった。アオカビが他の微生物との生存競争 に打ち勝って生き延びるために産生していた化学物質を人間に役立てたのである。これが最初の抗生物質であるペニシリンである。
つまりアオカビは、ペニシリンを作り出して他の微生物を殺し、自身が生き延びることをやっていた。人間はこれを、病原細菌を殺して生き延びることに応用した。フレミングはこの業績で1945年にノーベル賞を受賞している。
大村博士は、国内各地の土壌を採取しては研究室に持ち込み、スクリーニング(選別・検索)にかけてまず微生物の性質を説きあかし、次いで微生物が産生している化学物質のスクリーニングをして人間に役立つ物質を発見することを始めた。
ここまでが基礎研究であり、これを実用化するのが応用研究である。大村博士は米国に客員教授として招聘されているときに製薬企業のメルク社と連携することを取り付け、帰国後に本格的にこれを推進した。
「大村方式」という産学連携の契約を交わす
大村博士の研究室で微生物由来の化学物質を発見して特許を取得し、メルク社がそれを製剤などにして実用化をはかり、特許ロイヤリティを大村博士に支 払う。まさに産学連携であるが、これを大村博士は1973年、日本では産学連携という言葉もなかった時代から実際に始めたものであった。
大村博士がメルク社との産学連携で交わした契約は「大村方式」と呼ばれるものであり、いまでは普通のやり方になっているが当時は珍しかった。大村―メルク社で交わされた契約の大略は次のようなものである。
| 1. | 北里研究所は、土壌中の微生物が産生しているもので、特に家畜動物などに役立つ化学物質を抽出してメルク社に送る。 |
| 2. | メルク社はそれをもとに薬剤の開発を行う。研究成果として出てきた特許案件は、メルク社が排他的に権利を保持し二次的な特許権利についても保持する。 |
| 3. | ただしメルク社が特許を必要としなくなった場合は、その権利を放棄して北里研究所に移譲する。 |
| 4. | 特許による製品販売が実現した場合は、正味の売上高に対し世界の一般的な特許ロイヤリティ・レートでメルク社は北里研究所にロイヤリティを支払う。 |
非常に合理的な契約内容である。家畜動物などに絞ったのは、すでに人間用の微生物由来の化学物質は世界中で研究しているので、競争するのは大変である。むしろあまりやられていない動物に役立てる化学物質を発見しようという話になった。
家畜動物の病気を救ったり予防になる物質を実用化できれば、飼料代だけでも莫大な節約に結びつく。しかも動物に効くことが分かれば、それだけで動物実験になっているので人間に応用できる道が開けるのではないか。
大村博士の思惑は見事に当たって、動物製剤では世界的なヒット商品を生み、しかも人間への応用も実現して人類の福祉に多大の貢献をすることになる。
メルク社が大村博士に支払う研究費は年額8万ドル(当時は2400万円に相当)という当時としては破格の研究費供与だった。これは大村博士が招聘さ れたアメリカの名門大学、ウェスレーヤン大学のティシュラー教授がメルク社の元研究所長という縁があったからであり、大村博士はティシュラー教授にその手 腕を高く評価されたために実現した破格の条件でもあった。
大村博士はいつもビニールの子袋を持参し、土壌を採取しては研究室で分析していた。1975年、大村博士は静岡県伊東市川奈のゴルフ場近くで採取し た土壌の中から、新種の放線菌を発見してメルク社に送った。メルク社は、多様な化学物質を産生していることから動物の寄生虫に効くのではないかとにらんで 実験を続けると、果たせるかな家畜動物の寄生虫の退治に劇的な効果を発揮することが分かる。
この化学物質はエバーメクチンと名付けられ、その後、実験を重ねる過程で化学的に改良されてイベルメクチンという名前になる。ここでもイベルメクチンという名前で続けていきたい。
牛のお腹の中には、5万匹もの寄生虫が生息しているが、この寄生虫が牛の栄養分を相当に消費している。これを退治すれば飼料代が節約できるし、牛の 健康状態も良くなるので家畜の量産につながる。メルク社の実験によると、少量のイベルメクチンをたった1回飲ませるだけで寄生虫はすべて排除するという劇 的な効き目があることを実証した。
これはすぐに動物薬として発売し、たちまち動物薬の売上トップに躍り出てしかも20年以上も首位の座を守ることになる。
大村博士とメルク社で取り交わした産学連携の契約では、実用化で開発した薬剤の売上高に応じて特許ロイヤリティを北里研究所に支払う内容になっている。この契約に沿って北里研究所は1990年ごろから毎年15億円前後のロイヤリティ収入が入るようになる。
北里研究所は当時、経営が非常に大変な時期だったが、特許ロイヤリティの収益でたちまち建て直し、さらに埼玉県北本市に病院建設まで実現してしまう。
それだけにとどまらず、動物に効くイベルメクチンは、やがて人間にも効くことが発見される。対象となった疾病は、アフリカや南米の赤道地帯の熱帯地方で 蔓延しているオンコセルカ症(河川盲目症)という盲目になる恐ろしい病気の予防薬として劇的な効果が発見されるのである。
以下次号