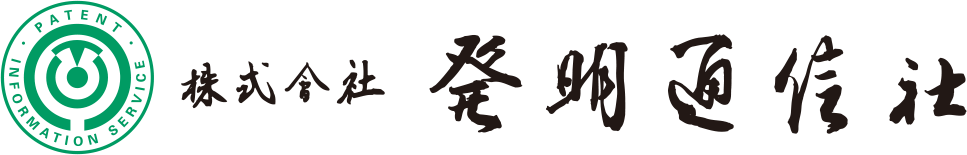均等
1998年2月24日に、その後の権利解釈に大きな影響を与えた最高裁判所の判決が出ました。つまり、「特許の権利を解釈するにあたっては、発明の本質的な部分でない些細な違いにこだわらずに判断すべし」との判決なのです。
こうした判断は、昔から「均等」と呼んで、特許の権利範囲を解釈するときに、どこまで字句(文言)の表現を拡大解釈できるかで、議論されてきたことなのです。
この判決前は、裁判所の判断がはっきりしてなく、少し厳密に、なるべく狭く解釈することが世の中の相場(この表現は適当でないかも知れませんが)でした。
法律の世界では、法律の法文に則って解釈が行われることが普通で、その法律がそもそもできた背景などを考慮して解釈することがおこなわれます。「立法の趣旨」などと表現しますが頭が痛くなりそうですね。
しかし、なかなか「立法の趣旨」だけで解釈できないことが少なくなく、そこに当事者が、それぞれに都合良く解釈することから争いが生まれる訳です。そして、どちらが正しいか公正な立場で判断してくれるのが裁判所です。
こうした判断の積み重ね(判例)が、法律の解釈をはっきりさせてくれるのです。そうした中でも、最高裁判所の判断となれば、それは重みが違います。
先の判決では、
(1)発明が解決する原理が同じかどうか。(違いが本質的な部分でない)
(2)作用や効果が同じかどうか。(対象製品と置き換えても変わらない)
(3)製品の製造時点で、置き換えることが簡単かどうか。(当業者が容易に想到)
(4)発明の出願前の公知技術を含まないこと。(公知例と同一、容易に推考)
(5)発明者や出願人が含まれないといったものでないこと。(意識的な除外)
が条件なのです。この五つの条件を満足するものは、少し表現が違っていても、その特許の請求範囲に含まれる。つまり、抵触すると判断すべきという判断なのです。
このような「均等」は、権利の解釈を拡大してくれるので、発明(技術的思想)を文字で正確に表現する限界を救って侵害者を排除してくれます。特許の権利者 を保護しようとすることでは結構な話です。しかし、反対の立場になると、広く広く権利が解釈され、技術思想が拡大解釈されることになり、今までは表現が下 手だから権利の範囲に入らなかったものまで含まれることになり、面倒な問題も発生します。
このような「均等の拡大解釈」の判決を頼りに、適当に権利範囲を書いておけば良いと考えるのは危険です。
「均等論」が議論される余地のない、すんなりと、誰が見ても文句なく、間違いの無い表現をしておくことが、有効な特許取得の条件であることをお忘れなく。
発明をしたら、その発明をこれ以上応用する範囲が見当たらないと思われることまで考えて、明細書を書くことを心掛けることです。
裁判に持ち込んで均討論に頼ることは、明細書作成する立場では避けるべきです。