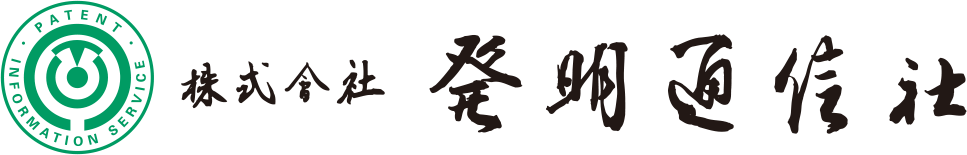ノーベル物理学賞と特許ロイヤリティについて(下)
産業技術でもノーベル賞を授与する時代
今回のノーベル物理学賞でまず感じたことは、産業界に近い業績でもノーベル賞 に手が届くことを改めて示したことであり、日本の科学界と産業史にとって画期的な結果となった。(写真はいずれもNHKテレビから)
ノーベル賞を授与される業績は、基礎研究の成果であり真理の新たな発見が最も価値ある業績とされてきた。20世紀のノーベル賞 受賞者の業績は、科学史そのものと言っても過言でないほど、輝かしい業績に彩られていた。
量子力学の勃興、遺伝子の構造の発 見からの生命科学の勃興などは、科学の歴史を書き換えた偉大な発見であった。しかしそのような科学の世界を揺るがすような真理の発見はしばらく 出ておらず、もはや出尽くした感がある。
これは筆者のような凡人のたわごとかもしれないが、大発見は少なくなった。IT(情報技術) の進展によって時間差と距離感がなくなり、科学の情報は世界中どこでもリアルタイムで取得できるようになった。
これは途上国も先進国も同 じ土俵に立ったことになり、いずれ途上国からも科学分野でのノーベル賞受賞者が出てくる時代になるだろう。
中国と韓国からまず出てくるだ ろう。
中村教授の受賞業績は産業界の手本になる
日亜化学工業という地方の企業を一躍、利益率のい い優良一流企業まで引き上げたのは、中村教授の手腕があったからである。前回取り上げた赤崎博士と天野教授の場合は、基礎・実用研究の成果を 豊田合成という企業に移転して貢献したものだが、中村教授の場合は丸々自社の事業に貢献したものであった。
企業の研究者でノ ーベル賞をもらうほどの業績を上げた例は、島津製作所の田中耕一博士の質量分析技術の発見がある。ノーベル賞をもらうほどの業績をあげながら島 津はこれを生かすことができず、実用化ではヨーロッパの企業に先を越された。
中村教授は違った。日亜化学の飛躍に貢献した第一 人者である。企業側に言わせれば、中村教授一人の貢献ではなく、多くの社員が参加し力を結集した成果だというが、ノーベル賞の選考では最初に扉 を開いた人にだけ授与することになっている。
その意味でも、中村教授の業績はゆるぎないものであった。
しかし中村教授 は、日亜化学を辞め「日本の司法は腐っている」と捨てぜりふを吐いてアメリカに去っていった。中村教授が日亜を辞めて研究者に転進する意向を明ら かにしたとき、アメリカのトップクラスの約10大学が招聘に動いたが、日本の大学や研究機関からの誘いはなかった。
評価できなか ったのは、企業や司法だけでなく日本の大学も研究機関も同じだった。


青色発光ダイオードの職務発明裁判を改めて総括する
青色発光ダイオード(LED)の職務発明の対価をめぐる中村教 授と日亜化学工業の裁判の一審判決(三村量一裁判長)は、中村教授の発明の対価は604億円と認定したが、博士の請求額が200億円だったことか ら満額の200億円の支払いを日亜側に命じた画期的な判決だった。
ところが二審東京高裁(佐藤久夫裁判長)は、本件控訴 審の争点になっている「404号特許」以外のすべての中村教授関連の特許や実用新案など195件を一括したうえで、一連の「一括発明」による日亜側 の利益を120億円と認定した。
そのうち中村教授の貢献度は6億円(5%に相当)とはじき出し、遅延損害金を含めて8億4000万円を日亜側が 支払うこととする和解を「強要」して決着した。
東京高裁は和解勧告の中で、判決を出してもこれ以上の金額が示されることはなく、 最高裁へ上告しても算定基準などを判断することはないので、中村教授が法廷で闘える機会は事実上失われていることを示唆したとされている。
高裁は強い「訴訟指揮」で日亜と中村教授に和解でこの裁判を決意させたものと受け止められており、それは判決を避けたという見方が当た っている。
一審判決では、中村教授が青色LEDの研究開発に取り組んだいわば「創業者貢献」を認めたものであり、判決文全 体にその考えがにじみ出ていた。
高裁の判断では、争点になっている404号特許だけでなく、中村教授に関連する特許・実用新案などすべて の知的財産権を一括して対価の対象にしたものであり、一審とは違った土俵での和解条項にした。
高裁はその理由を「(中村教授 関連の)すべての職務発明の特許の権利について和解し、全面的な解決を図ることが極めて重要」(要旨)と述べている。しかしこれは、裁判所がやる べきことから逸脱している。
日本の特許裁判は、真理の究明による判断ではなく、文言・レトリック勝負であり、法学部出身の法律家 はこれを「技術で裁くのではなく法理で裁く」と語っている。実体は技術オンチの裁判官が裁くものであり、これでは真理の究明からは程遠い結果になっ てしまう。


中村教授が発明した青色LED訴訟をめぐる一審判決と二審和解の結果を見ると、日本の裁判所の限界を示していることを図らずも今回のノーベル賞に よって明確に示したことになる。
企業は自社の研究社員に対し「ノーベル賞をもらうほどの技術発明をせよ」とはっぱをかけているが、価値ある 発明をしても企業も社会も大学も正当な評価ができなければ、研究者は外国へ逃げていくことになるだろう。
今回のノーベル賞 は、発明の正当な対価を改めて考えさせた日本にとって歴史的な出来事だった。