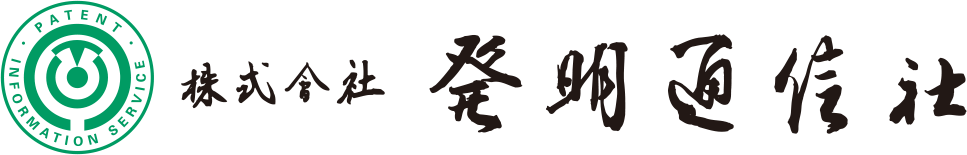いつまで経っても成熟しない日本の司法現場
一番遅れている司法府
三権分立国家で出発した1945年の戦後の日本だが、三権の中で最も進歩しなかったのは司法府という説が、最近にわかに言われ始めている。筆者の35年間の新聞記者時代に取材・執筆を通しても、そう思うことがたびたびあった。
まず、行政訴訟はほぼ原告が敗訴する。元裁判官で民事訴訟法の大家、瀬木比呂志先生の「絶望の裁判所」(講談社現代新書)を読むと、司法界の後ろ向きの信じがたい赤裸々な姿が浮かび上がってくる。
日本は諸外国に比べて突出して「和解」が多い。和解は裁判所が「仲介」して紛争を終わらせる制度だが、原告・被告・裁判所の三者にそれなりのメリットがある。原告・被告は立場が真逆だが、裁判所にはどのようなメリットがあるか。瀬木先生は、判決文を書かなくても訴訟を終結させ、それが裁判官の処理実績になると語っていた。
 最高裁大法廷(最高裁ホームページより転載)
最高裁大法廷(最高裁ホームページより転載)
裁判所の「権威」に名を借りた解決法なのか
こうした見解は、多くの弁護士も気が付いている。裁判所から和解を持ちかけられたら、代理になっている訴訟案件の判決は「考えた方がいいですよと、暗に語っているように感じた」という弁護士が多い。裁判所が和解を持ちかけることによって原告・被告にそれなりのプレッシャーをかけ、和解に持ち込むことを狙っていると解釈する人は多い。
知財訴訟に和解が多いことに疑問を持っている専門家も多い。特許侵害訴訟に代表される知財訴訟は権利を持っている人だけのものではなく、その権利を利用しようとしている人も大きな関心がある。
それが和解で解決すると、どの争点で折り合ったのか、権利侵害はあったのかなかったのか。どんな条件で和解が成立したのか。金銭の譲受があったなら、その金額はいくらだったのか。それらがすべてベールに覆われたままになってしまう。
特許登録情報は、最高の技術開発情報であり、しかも公開したうえで強大な権利を出願から20年間、国家から付与される。その権利をめぐって権利者と利用者が裁判紛争になった場合、判決が出ないで和解で解決したなら、その特許内容と関連する技術開発をしている人々には、争点内容が全く不明のままになってしまう。研究開発や技術の進歩にも支障を与えるだろう。知的財産権は当事者のものだけでなく、あらゆる人々が関心をもっている権利であり、公共の財産と考えてもいい。
先ごろ、アメリカ連邦最高裁スティーヴン・ブライヤー判事(83)が引退演説を行い、その高潔で分かりやすい演説内容が反響を呼んでいる。https://www.youtube.com/watch?v=Lv7WkW7z4hQ
「米国民はこの合衆国憲法を受け入れ、法の支配の重要性を受け入れた我々は人権と民主主義に基づいた国に生きている」
今は亡き連邦最高裁判事ルース・ベイダー・ギンズバーク判事は「立法と行政は国民を守り、司法は憲法を守る」と語っていた。
アメリカの最高裁判事の演説を聞いて感じたことは、日本の司法府は今こそ真の独立した判断を示すことが必須であると思った。司法府の意味ある存在こそ下降線をたどっている日本を建て直す最大のカギになると考え、このコラムを書いた。